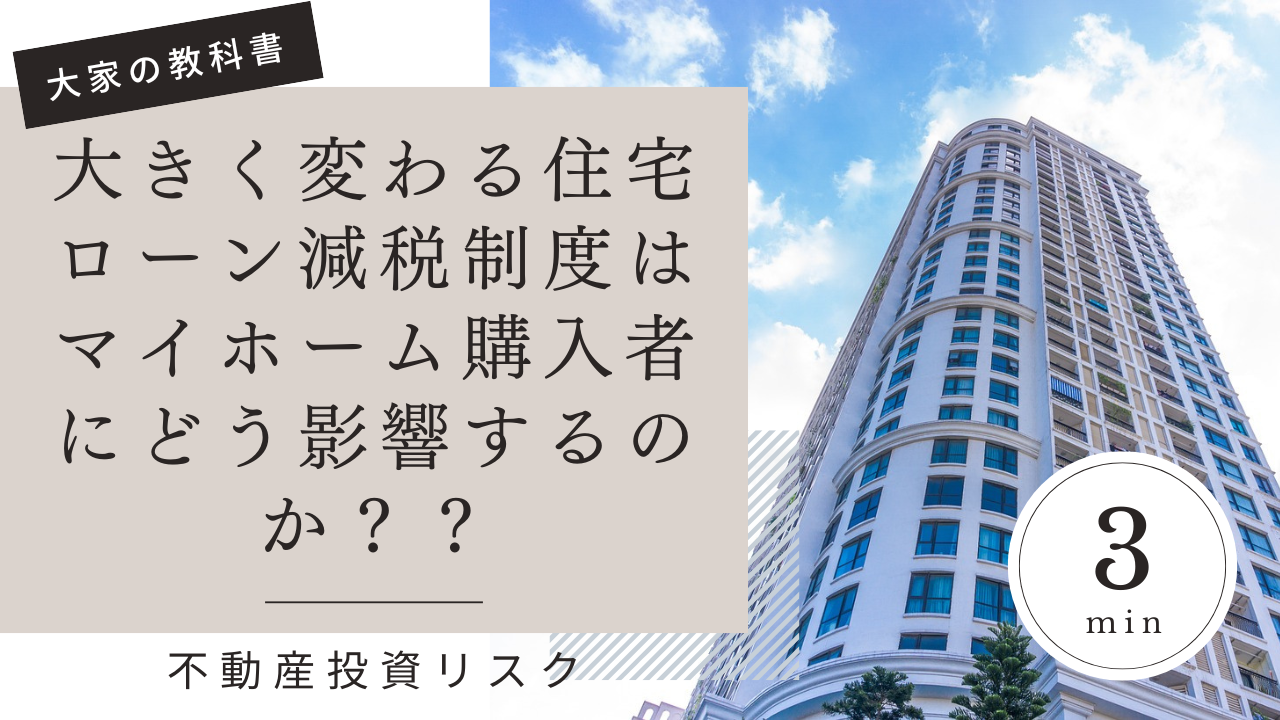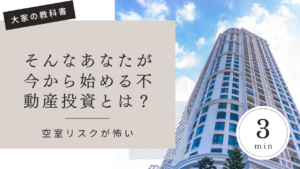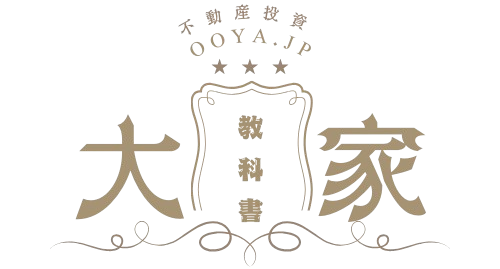政府与党が2021年度税制改正で検討している住宅ローン減税の見直しの全容が明らかになってきました。
これまで、マイホーム購入者に多くの恩恵を与えていた住宅ローン減税ですが、ここにきて制度が大きく見直されそうです。
これによりマイホーム購入者の金利に対する考え方が大きく変化し、住宅販売会社への影響も計り知れないものになると考えられます。
その全容を紐解いてみたいと思います。
住宅ローン減税の制度と仕組みについて
まずは、住宅ローン減税についておさらいしてみましょう。住宅関連業界や金融業界、税理士業界では、有名な制度でした。住宅ローン減税が広く知れ渡り注目を集めはじめたのは、2019年に消費税が8%→10%にアップする際のことです。
2019年10月の消費税率の引き上げを受け、住宅ローン控除の期間がこれまでの10年から13年へと、3年間延長されることになりました。このニュースによって住宅ローン減税の存在を知った方も多いと思います。
住宅ローン減税とは
住宅ローン減税とは、マイホーム購入者の経済的負担を軽減するための制度です。マイホームを住宅ローンを利用して購入する際に一定の割合の金額が所得税から控除されます。
この制度がマイホーム購入者の背中を後押しするものとなり、巷では『儲かる住宅ローン』とか『金利錬金術』と言われていました。
住宅ローン減税の仕組みについて、さらに細かく見ていきます。下の図をご覧ください。
一般的に、収入から経費や各種控除によって減額され、年間の所得が確定します。その所得に応じて所得税や住民税などを支払っているわけですが、住宅ローン減税は、これらの税金か減税される仕組みになっているのです。
これは制度上、非常に”おいしい”仕組みであることは間違いありませんね。
最近の低金利によって制度の欠陥が浮き彫りに
もともと、住宅ローン減税は昭和61年にスタートした歴史のある制度です。スタート当時の日本はイケイケの時代で、当時は住宅ローン金利も5%近くあったと言われています。
繰り返しになりますが、住宅ローン減税は『毎年12月31日時点の借入残高の1%(上限40万円)を所得税・住民税から直接減額』する制度です。
住宅ローン金利が5%もあれば、購入者の負担を考えて、『借入残高の1%を所得税からの減額もやむなし』といったところですが、現在の金利事情を考えれば、この制度の歪みに誰もが気が付くでしょう。
特に、最近ではコロナ対策で真水の注入や税の徴収の猶予などを実施している状態ですので、このような歪みに対しては敏感になってもおかしくありません。
住宅ローン減税の「1%控除」の仕組みについては会計検査院が低金利時代に合わないと問題視している。借入金利が控除率の1%を下回ると、控除額が支払利息額を上回る「逆ざや」のような過度な恩恵を受ける人が出る場合があるためだ。政府・与党は21年度改正では現行の控除額の仕組みを維持する一方、22年度にも見直す方針を税制改正大綱に明記する方向で調整している。
2020年12月5日 日本経済新聞より抜粋
実際の利用事例について
最近では、住宅ローンの金利は1%を割ることは決して珍しくありません。実際に住宅ローンでマイホームを購入した人のうち、80%近くが1%未満の金利でローンを組んでいるというデータも出ています。
ですので、ほとんどの方が住宅ローン減税によって、制度が意図する金額以上の減税を受けているるのです。ただ、決してこれは悪いことではありません。制度と金利を上手に活用しているだけに過ぎません。
一例ですが、3,500万円の住宅ローンを金利0.4%の35年ローンで購入したとします。
その場合、月々の返済額は約9万円。一年目の返済額は1,071,792円となります。そのうち、元金が933,508円、金利が138,284円です。一年目の住宅ローン残高の1%、即ち、340,664円が減税されることになります。
この場合、金利で138,284円支払っていますが、1%の住宅ローン減税によって、202,381円が得をする計算になります。もちろん、金利が0.5%、0.6%と高くなればその分、儲け(?)も減ってしまいますが、見事に制度のギャップをついたものとなっています。
住宅ローン減税の控除額見直しへ
このような”おいしい”制度はいつまでも続くはずはありません。政府はこのような歪んだ制度を見直すタイミングを虎視眈々と窺っていたのでしょう。例えば、2019年の消費税増税のタイミングにおいても可能だったと思いますが、消費税増税という施策が国民の反感を買うため、手が付けられなかったのだと思います。
今回に関しては、コロナ対策により、助成金や給付金、税の徴収猶予などを政策として実施しているため、歪みに関しては是正するという意味において筋を通せる絶好のタイミングなのでしょう。
住宅ローン減税の見直しのポイント
2021年度税制改正で検討されている住宅ローン減税を見直しの全容が徐々に明らかになってきました。
まず、2021年にスタートする部分と2022年まで猶予を持たせる部分に分かれていることに注目します。
13年間の控除について
消費税増税時に改正された、13年間の控除を受けることができる特例については、入居期限を2022年末まで延長するようです。
入居面積について
対象物件の面積については緩和されます。従来の床面積50㎡以上から40㎡以上に緩和される予定です。ただし、50㎡未満の住宅を購入する場合は、1,000万円の所得制限を設けるようです。
遡りはなし
制度の見直しについては、2021年、2022年に実施される予定ですが、「遡りの対応」はないようです。ですので、2021年は住宅販売の駆け込み需要が十分に見込まれる年になりそうです。
住宅ローン減税について
住宅ローン減税については、高金利時代に用意された制度となり、現在では、支払い控除額が支払い利息を大きく上回るような、逆ザヤ状態となっています。
21年度改正では、見直しが入らなそうですが、22年度改正に向けた議論では重点的な課題として着手されそうです。
具体的には、従来の一律『借入残高の1%ルール』から、『借入残高の1%または支払利息総額』を所得税・住民税から控除するといったルールで落ち着きそうです。
つまり事実上は、利息分だけが控除の対象になるということになります。
今までは、変動金利で表面的な金額を低く見せつつも、住宅ローン控除で減税されるといったセールストークのキレがなくなる一方で、金利上乗せ型の提案や保証を強化するような提案が主流になってくると考えられます。
今後の見通しについての見解
恐らく、住宅ローン金利が大幅に上がらない限り、2022年度改正では住宅ローン減税のルールは変更されるでしょう。
それによって、住宅ローン市場ではどのような動きが主流になるのかを、少し考えてみたいと思います。
低金利から高金利へ
まず、住宅ローンを使って住宅を購入する場合の選択肢は狭まるでしょう。
変動金利を採用するメリットが薄まり、フラット35が主流になることが予想されます。変動金利と比べて、フラット35は金利が高いことがデメリットです。ただし、1%未満金利でローンを組むこと自体に意味がなくなるわけですから、最低でも1%の金利が主流になるでしょう。
具体的にはこうです。
- 金利上乗せ団信を付帯するか?死亡団信のみか?
- 事務手数料や保証料は一括型か金利上乗せ型か?
このようなやりとりが生まれてきます。
なぜなら、利息分のみが控除の対象になる見通しだからです。
金融機関としては住宅ローンから得る収益が上がりますが、購入者にとっては控除されるお金とはいえ、10年間のみなので、事実上負担が大きくなってしまいます。
団体信用生命保険の特約加入者が増加
団信保険料に金利上乗せプランを付帯するケースが増えてくる可能性があります。
従来の死亡団信のみなのか、三大疾病保障をつけるのか、このようなやりとりが増えてくるでしょう。
金利を上乗せしても国が払ってくれるという理屈です。
ネットバンクでの住宅ローン契約者が減少
先ほど、保証料について『一括型』か『金利上乗せ型』かの話をしましたが、ネットバンクで住宅ローンを組む場合は、選択肢に金利上乗せ型がありません。
保障料の金利上乗せができる、一般的な金融機関への選択肢が増えてくることは間違いなさそうです。
これも、上乗せされた金利は国が払ってくれるという理屈です。
住宅ローン減税は10年間であることにも注意が必要
住宅ローン減税の制度が見直される可能性が高まっています。
『借入残高の1%または支払利息総額が控除される』ことで、制度自体は現行と比較して”改悪”と言わざるを得ません。
そのため、制度を少しでも有効活用しようと、様々な金利上乗せオプションを活用して”元を取ろう”と考えがちになりますが、制度の有効期間は10年であることを忘れてはいけません。
11年目以降の支払い額などを確認しながら、支払いのバランスを保つ必要があります。
いずれにしても、金融機関の住宅ローン金利の動きからは目が離せませんね。